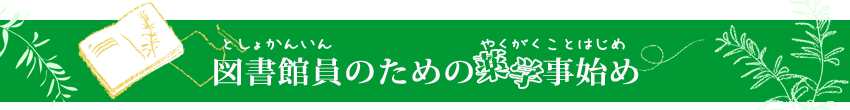薬学図書館員基礎知識
電子ジャーナル
電子ジャーナルとは
1990年代から従来の冊子体の学術雑誌は電子化とオンライン化で、インターネットでアクセスできる形態へと移行していった。電子ジャーナルの利用により、利用者は論文を読むために図書館に足を運ぶ必要はなくなり、ネットワークに接続できれば、研究室などのPCからいつでも論文を読むことができるようになった。その他にも、論文の全文検索ができること、引用文献のリンクから次に読むべき論文に容易にアクセスできること、文献管理ツールを利用して自分の文献リストを容易に作成できること、またそれを研究仲間と共有できること、などのメリットがあり利便性が大きく向上した。図書館にとっても、配架場所を必要としないことで書架の狭隘化の心配がないこと、受け入れ・配架などの作業がないこと、製本の必要もないこと、利用実績が把握できること、などの多くのメリットがある。
一方、デメリットとしては、価格が高騰していること、冊子体の雑誌のように所蔵するわけではなく、契約期間中のアクセス権の保持であること(契約中止後アクセス権がなくなることが多い)、契約形態、利用条件が複雑なことが挙げられる。
契約形態
購読契約の種類
電子ジャーナルの契約形態は、大きく分けて3種類あり、いずれも「年間を通した購読契約」が基本となっている。
- 個別タイトル契約: 1タイトルずつ契約する方法
- セット契約: 姉妹誌などセットになっている雑誌をまとめて購読する方法
-
パッケージ契約:
- 同一の出版社や学会などから刊行される個別タイトルをまとめたパッケージ単位で契約する方法 過去の購読雑誌の購読額に、購読してない(非購読誌)のアクセス権をプラスした契約額になることが多い。アクセスできるジャーナル数は飛躍的に多くなるが、購読額が高いため予算が厳しくなれば見直しが必要となる。また、過去の購読額ではなく自社のジャーナルをひとつのデータベースとして価格設定する「データベースモデル」という契約方法も出てきている。
- アグリゲータと呼ばれる業者が提供する、さまざまな出版社や学会から分野別にタイトルを選定し販売するパッケージ。アグリゲータが設定する価格で購読することとなる。
- ★大学等の規模や分野によって、どの形態で契約するのが有利であるかは異なる。
サイトライセンス、FTE、Tier、Bandなど
サイトライセンスとは、大学などの組織単位で利用量無制限の電子ジャーナル利用権を一定期間許諾を受ける契約のこと。
サイトとは具体的には大学等の敷地を示すことが多い。出版社によりサイトの定義は異なり、1キャンパスごとに1サイト、1大学で1サイトなどの契約方法がある。
FTE(利用者規模)は価格を算出する指標の一つで、構成員の数で大学等の利用規模を何段階かに分け価格設定をすることが多い。TierやBandも、利用規模による価格算出指標の方法である。
★ FTEは、Full Time Enrollment
★契約時には、これらの条件を十分に把握したうえで、出版社・業者と交渉することが肝要である。
同時アクセス
個別タイトル契約やセット契約の場合には、同時アクセス数で価格が設定されることがある。
一方、パッケージ契約の多くは、同時アクセス無制限であることが多い。
転換契約
オープンアクセスが進展する中(下記「オープンアクセス」の項参照)、主に図書館が支払うパッケージ契約の購読料と研究者が論文をオープンアクセスにするため支払う論文掲載料(APC:Article Processing Carge)を合わせて支払う契約形態。近年、欧米を中心に広がり日本でも研究を重視する大学で移行が進みつつある。オープンアクセスの推進を目指す中で研究者のAPC負担を軽減し研究を促進させること、支払額総体で大学等の費用負担を軽減することが見込まれているが、自機関の研究者の論文投稿状況や投稿額と電子ジャーナルの購読額を入念に分析し、自機関にとってメリットがあるかどうかを検討して進める必要がある。
利用方法
利用する(購読したジャーナルにアクセスする)には、いつかの方法がある。
-
IPアドレス認証
一般的には、サイトライセンス契約機関のIPアドレスからのアクセスを可能とするIPアドレス認証が多い。この場合、同時アクセスの制限の無いことが多い。 -
ID/パスワード認証
個別契約やセット契約にみられるのが、ID/パスワード認証である。アクセスの際にID/パスワードが必要なため制限がかかり、同時アクセス数も限定されることがあるが、契約金額の抑制という効果もある。 -
シングルサインオン(SSO)
ID/パスワードを出版社やジャーナルなどのサービスごと登録すると、提供者と利用者双方でのID/パスワード管理が煩雑になる。近年では、サービスの提供者側が、ID/パスワードの認証を利用機関側に委ね、利用者が単一のID/パスワードで多くのサービスを利用できるようにするシングルサインオンが増えてきている。学術サービスでは、多くのサービス提供者とこのような認証連携を効率的に行うため、予め定められた規程を相互に運用する連合体(フェデレーション)を形成し、一度の認証で参加出版社の全ジャーナルが閲覧できる環境が実現されている。国内の学術機関と学術サービス提供機関のフェデレーションとして、NIIが学認(GakuNin)を運営している。企業でも類似のサービスがある。 -
リモートアクセス
契約機関の敷地外(学外(出張先、自宅等))からアクセスする方法。まずは契約時の利用条件でリモートアクセスの可否を確認しておく。利用者にとってはどこからでも利用可能となり利便性が高いので、リモートアクセス可の場合は、以下のいくつかの方法で実現することが推奨される。
機関内認証により機関内ネットワークにアクセスするVPN方式、プロキシサーバー(EZproxyなど)を経由する方法。
なお、前述の学認でもリモートアクセスが可能になっている。いずれの場合も、機関内の情報基盤を担当する部署と相談のうえ、自機関の方針に合った認証方法で実現することが必要。
利用条件
利用条件は、契約時に十分に把握しておくことが必要である。
-
利用者の範囲
自機関に所属する職員および学生を利用者とすることが想定されるが、常勤、非常勤など職員の範囲、学生ならば正規の学生のみか否かなどをチェックしておくこと。また図書館に入館した部外者(Walk in userという)は利用可能かどうかなどもポイントとなる。 -
ILLの可否
相互協力(ILL)による他大学からの複写依頼に対応できるかどうか、可能な場合は、紙か電子版かも確認が必要である。プリントアウトした紙であればILL可能であることが多い。 -
過去分の利用範囲
契約中は、契約機関プラス過去分が提供されるなど有利な条件で利用できることもあるが、契約終了と同時に過去分は利用できなくなることも多い。契約条件をよく検討して過去分の利用にも配慮する必要がある。 -
その他
授業での利用、テキストデータ・マイニングの可否、利用統計取得の可否、契約終了後の扱い(Post Cancellation Access)などをチェックしておきたい。
利用統計
電子ジャーナルは、冊子体と違って明確な利用統計が取れるので、正確に取得して購読継続可否など見直しに活用できる。新規に購読を検討する場合には、トライアルを実施し利用件数を事前に確認することも重要である。
-
COUNTER統計
海外出版社や学会では、利用統計の国際標準であるCOUNTERに準拠した統計を提供していることが多い。これを取得し一元管理すれば、標準化した利用データによる出版機関を横断した比較が可能となる。
COUNTER準拠でない統計しか提供されない場合は、他の出版社等の統計との比較が困難となり、そのジャーナルの利用の経年変化等を把握するのみとなる。
このほか、自機関のサーバーを経由して実績ログを収集するなど、機関独自で統計を取得する方法もある。
アクセスへのナビゲート
-
プラットフォーム
電子ジャーナルは、その提供元の出版社、学会、アグリゲータ(EBSCO、ProQuest、JSTOR、Ovidなど)が構築・提供するプラットフォームに搭載されている。これらのプラットフォーム上では、管理者用に利用統計や各種設定ができる。海外では、Elsevier社のScience Directや、Atypon、Highwire、日本の電子ジャーナルプラットフォームには、J-Stage、医書.jpなどがある。 -
リンクリゾルバ
自機関のOPAC等の検索結果から、利用可能な電子ジャーナルや電子ブックなどの他のリソースへのリンク(ナビゲート)を提供するツール。利用者はOPAC検索から電子ジャーナルがあれば直接そのジャーナルを見ることができる。また無い場合はILL申し込みへナビゲートするなどの機能もある。 -
A-Zリスト
電子ジャーナルをアルファベット順や分野別に一覧したり、キーワード検索ができるリスト。 -
ディスカバリーサービス
OPACに搭載された紙の資料とともに、契約しているデータベースや電子ジャーナル、電子ブックなどの様々な電子資料をまとめて検索できるツール。 -
ナレッジベース(Knowledge Base)
ナレッジベースとは、世界中の出版社や情報システムベンダーなどから電子リソースのタイトルやURLなど簡易なメタデータを網羅的に収集し、最新の状態で保持しているデータベースである。図書館はナレッジベースから自機関で利用可能な電子リソースを選択して設定することで、電子リソースを容易に管理し、アクセスを提供することができる。上記のリンクリゾルバ、A-Zリスト、ディスカバリーサービスは、すべて自機関のナレッジベースを基盤として機能している。自機関のナレッジベースは、購読中の電子ジャーナル等の管理上のデータベースとしての役割を果たすことができる。 -
Google Scholar
電子ジャーナルは論文単位でGoogle Scholarなどの検索サイトでも検索できる。購読中のジャーナルは利用範囲(IPアドレス内、リモートアクセス内等)内であれば、そのまま本文を閲覧することができる。
様々な購読・利用方法
-
Pay per view(PPV)
年間購読が予算上または利用の偏りなどからすべて継続維持することが困難となった場合、その代替手段として、1論文ごとに閲覧料金を支払うPay per view(PPV)を導入する方法がとられることがある。出版社によってPPVの販売方法が違う(トークン方式や機関向け販売など)ので、購読方法と利用方法をよく検討すること。 -
バックファイル(Back File)
過去に刊行された電子ジャーナルコンテンツのこと。アーカイブと同じ意味で使われることが多い。
出版社等によっては、バックファイルを買いきりで恒久アクセス権付きで別途販売することがある。一度の支払いでアクセス権がなくなることはないので、自機関に真に必要で過去分も重要なジャーナルは、バックファイル購入して恒久アクセス権を取得するとよい。
なお、NIIが整備するNII-REOからは、Springer LINK(1832-1999),Oxford University Press(1996-2003),Taylor& Francis(1798-1996)がナショナルアカデミックライセンスとして提供され、日本国内のNIIに機関登録した学術研究機関であれば閲覧が可能となっている。
参照:NII学術コンテンツサポート https://support.nii.ac.jp/ja/reo/oja/oja_db -
ダークアーカイブ(Dark Archive)
出版社の倒産、自然災害などによって、電子資料が提供されなくなった場合に備えた電子的アーカイブ。 通常はアクセスできないが、非常時に限り利用することができるようになる。代表的なダークアーカイブには、CLOCKSS(クロックス)やPortico(ポルティコ)がある。機関ごとにCLOCKSSやPorticoに年会費等を支払う形で利用できる。
オープンアクセス
オープンアクセスとは
オープンアクセス(OA)とは、査読付きの学術論文等について「インターネットにアクセスできるようにすることとそれ自体を除く経済的、法的、技術的な障壁なく分権を利用できるようにすること。」(参考文献
2)と定義されている。電子ジャーナルの高騰が続く中で、経済的に購読を断念する学術機関が増えていけば、学術論文は限られた人しか読めなくなってしまう。これを危惧し研究成果は公平に共有されるべきであるという考え方のもとに、オープンアクセスは世界的な潮流となりつつある。欧米の研究助成機関では、公的助成を受けた研究成果出版物はオープンアクセスで公開しなければならないとの動き(2018年9月欧州cOAlition
S
によるPlanS)があり、加えて公開猶予期間(エンバーゴ:Embargo)なしに即座にオープンアクセス化すべきとの方針(2022年8月、米・科学技術政策局(OSTP)「即座OA方針」参照:https://rcos.nii.ac.jp/miho/2022/08/20220827/)などが公開され、OAに向けての流れは大きくなっている。
このような動きの中で、オープンアクセス(以下、OA)は、以下のような方法で実現されている。
-
Green OA(機関リポジトリ、主題リポジトリなど)
大学等が運営する機関リポジトリや分野ごとの主題リポジトリなどに掲載・公開する方法をGreen OAという。機関リポジトリの場合は、大学図書館等が運営するリポジトリに論文原稿(著者版)を登録すれば、掲載料なしで公開することができる。ただし、公開の条件として出版社による制限(ジャーナル紙面上のレイアウトされた原稿ではなく著者が持つ最終版原稿のみ公開可能とか一定期間のエンバーゴを経た後など、制限は出版社によって異なる)や、共著者の同意などが必要となる。
出版社の論文利用条件・著作権規定等を調べるには、Sherpa Romeo(シェルパロメオ)を利用するとよい。
参照:Sherpa Romeo https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/ -
Gold OA
既存の出版社がOAジャーナルを発行し、論文著者から掲載料(APC:Article Processing Carge)を徴収する等出版社主導のOAをGoldOAという。掲載論文すべてがOAであるものをフルOA誌、有料(購読誌)のジャーナルに掲載された論文のうち著者が追加料金(APC)を支払うことでその論文のみOAとなるものを、ハイブリッドOAという。
著者が支払うAPC額も年々大きくなっており、高騰する購読料と合わせて大学等の研究機関の財政を圧迫するに至っている。このため、電子ジャーナルの転換契約(購読料とAPCを総体で支払う契約方法・上記 1.2契約形態 転換契約の項参照)へシフトする大学等も現れている。 -
★ハゲタカジャーナル
APCを徴収しOA査読誌の体裁をとりながら、APC収入だけを目的として、実はろくな査読もせずに質の低い論文を掲載するジャーナルをハゲタカジャーナル(Predatory (捕食・略奪の意味)Journal)、粗悪学術誌という。自機関研究者から投稿先のジャーナルの信頼性について相談を受けたら、DOAJ( Directory of Open Access Journals、DOAJ:オープンアクセス学術誌要覧)などにより、そのジャーナルの評価や信頼性を確認した方がよい。
参照:DOAJ https://doaj.org/
プレプリント
学術雑誌への掲載に先行して査読前の論文をインターネット上で公開・流通させるためのプレプリントサーバーから公開された論文。従来、物理学、数学、経済学等の限られた分野において、より迅速にアイディアや研究成果を共有し議論するための学術コミュニケーションのチャンネルの一つとして活用されてきた。近年、特に2016年以降、プレプリントサーバー数は飛躍的に伸び、多くの分野でも利用されるようになった。そのメリットは、研究成果の迅速な配信、可視化、研究コミュニティからのフィードバック、発見とアイディアのプライオリティ(先取権)の取得などがあり、著者は無料で成果を公開し、読書も無料で読むことができる。また従来、プレプリント論文を先行出版として投稿受付を拒否する学術誌も多かったが、通常の学術誌では掲載までの時間がかかることから、プレプリントとして発表された論文の掲載を認める出版社も増えてきた。このようにプレプリントと学術誌の共存の例がみられるようになってきており、プレプリントの隆盛に繋がっているとの考えもある。主なプレプリントサーバーは以下の通り。
-
BioRxiv:生物化学、医学、生物学分野を対象
コールド・スプリング・ハーバー研究所(Cold Spring Harbor Laboratory, CSHL)が運営 -
arXiv
物理学、数学、コンピュータサイエンス、統計学、電子工学など理系で新規性を担保するために誕生したプレプリントの起源となるサイト。コーネル大学図書館が運営 -
ChemRxiv
化学分野のプレプリントサーバー。アメリカ化学会(ACS)、英国王立化学協会(RSC)、ドイツ化学会(GDCh)、中国化学会(CCS)、日本化学会(CSJ)の協力のもとACSが管理・運営 -
PrePubMed
医学生物学系プレプリント論文の検索エンジン -
medRxiv
ヘルスサイエンス分野を対象。CSHL、BMJ、イェール大学が設立。
知っておきたい主な用語
-
Altmetrics(オルトメトリクス)
ソーシャルメディアでの参照数等によって研究成果の有用性を多角的に評価する指標 -
DOI(ディーオーアイ)
デジタルオブジェクト識別子( Digital Object Identifier、略称DOI)は、インターネット上のドキュメントに恒久的に与えられる識別子。恒久的に変わらないので学術論文にDOIを付与することは学術界では標準となっている。論文のほかにも研究データなどにも付与することができる。 -
OpenURL(オープンユーアールエル)
ウェブ上に公開された図書館システムや論文管理システムとの間で、本や雑誌・論文の情報を標準的にリンクする方法としてOpenURLが提唱されている。リンクリゾルバなどのツールはOpenURLにより機能している。 -
Orcid.iD(オーキッドアイディー)
同姓同名など研究者名を同定するために、研究者識別子を用いることが標準となってきている。
Orcid.iDは代表的な研究者識別子で、一人の研究者に対して一つの一意な番号を付与することができる。その識別子に対して論文などの業績を紐づけることで、自身の研究成果が正しく自分の業績だと認識される。 -
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)
インターネット時代のための新しい著作権ルールで、作品を公開する作者が「この条件を守れば私の作品を自由に使って構いません」という意思表示をするためのツール。CCライセンスでは、ライセンス条件を明確に示すための4種類の条件がある。著者はこの条件を組み合わせて自分の作品・著作の利用条件を示すことができる。 参照:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン https://creativecommons.jp/licenses/#licenses
参考文献
-
「はじめての電子ジャーナル管理 改訂版 JLA図書館実践シリーズ 35」
保坂 睦著 日本図書館協会 2023.06
ISBN:978-4-8204-2300-3 -
「オープンサイエンスにまつわる論点 変革する学術コミュニケーション」
南山 泰之 編、池内 有為,尾城 孝一,佐藤 翔,林 和弘,林 豊著
一般社団法人 情報科学技術協会 2023.06
ISBN:978-4-88367-380-3