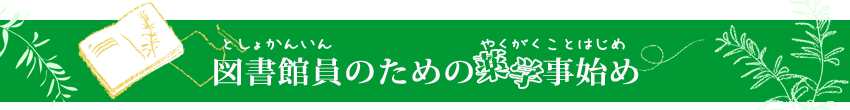概論
日本の薬学教育
 大学で薬学を学ぶ
大学で薬学を学ぶ  日本の薬学教育制度
日本の薬学教育制度  日本薬学会モデル・コアカリキュラムについて
日本薬学会モデル・コアカリキュラムについて  日本薬学会モデル・コアカリキュラムの内容
日本薬学会モデル・コアカリキュラムの内容
大学で薬学を学ぶ
大学の薬学教育は、2006年度より6年制と4年制になりました。6年制では薬剤師養成のため臨床薬学を重点的に学び、4年制では薬学研究者の育成を目的とした創薬研究中心の薬学教育を行なっています。 大学で学ぶ内容は、社会薬学、基礎薬学、医療薬学、衛生薬学、臨床薬学、薬学研究などです。
日本薬剤師会・薬学教育委員会が1996(平成8)年に公表した薬学教育の改善に関する答申は、教育の根幹に生命倫理を据え、医療人として必要な医療倫理・社会薬学系、薬の科学技術の基礎を支える生命・分子薬学系を薬剤師を養成する教育の基礎学とし、この基礎の上に医療薬学系、創薬化学系、衛生薬学系を応用薬学系を学ぶ、としています。 ※1
薬学系の学部学科を設置している大学は全国に70以上あります。薬剤師になるには薬学部に入学し、6年間の課程を修了後、薬剤師国家試験に合格する必要があります。
※1 薬学概論 改訂第4版増補 辰野高司ほか編, 遠藤浩良ほか著 南江堂 2005 p182 抜粋
薬学教育モデル・コアカリキュラムについて
薬学教育モデル・コアカリキュラムは、各大学が策定する「カリキュラム」のうち、6年制薬学教育において共通して取り組むべき「コア」の部分を抽出し、「モデル」として体系的に整理したもので、このモデル・コアカリキュラムを参考としながら各大学はカリキュラムを編成することが求められています。平成14年の初版から平成25年の改訂を経て、令和4年度改訂版が作成されました。
日本薬学会モデル・コアカリキュラムの内容
モデル・コアカリキュラムは、以下のように5つに分かれています。
- A:薬剤師として求められる基本的な資質・能力
- B:社会と薬学
- C:基礎薬学
- D:医療薬学
- E:衛生薬学
- F:臨床薬学
- G:薬学研究
令和4年改訂では、「未来の社会や地域を見据え、多様な場や人をつなぎ活躍できる医療人の養成」をキャッチフレーズに掲げられました。これは、医学・歯学・薬学教育の3領域で統一されたものです。
以下簡単に内容を紹介いたします。
A:薬剤師として求められる基本的な資質・能力
薬剤師を目指す学生は、卒業後も継続的に「A 薬剤師として求められる基本的な資質・能力」を身に付ける努力を続け、常に高い資質・能力を目指して生涯にわたってより良い医療人となるために研鑽を積む必要があります。大項目B〜Gの全ての内容が、「A 薬剤師として求められる基本的な資質・能力」に掲げられた個々の資質・能力を身に付ける上で重要です。
B:社会と薬学
薬学教育モデル・コア・カリキュラムにおける「A 薬剤師として求められる基本的な資質・能力」を生涯にわたって培うために、「C 基礎薬学」、「D 医療薬学」、「E 衛生薬学」、「F 臨床薬学」、「G 薬学研究」を学ぶための基盤として、薬剤師の責務、求められる社会性、社会・地域における活動、医薬品等の規制、情報・科学技術の活用について学修し、医療、保健、介護、福祉を担う薬剤師としての自覚と、社会の変化や多様化を踏まえて国民の健康な生活の確保に貢献する能力を身に付けます。
C:基礎薬学
基礎薬学の領域内の学修レベルには階層性(順次性)があり、最も基盤となるのが物理化学(「C-1 化学物質の物理化学的性質」)、化学(「C-3 薬学の中の有機化学」)及び微生物学を含む生物学・生化学(「C-6 生命現象の基礎」)です。これらの科目の学修によって、本大項目内の分析科学(「C-2 医薬品及び化学物質の分析法と医療現場における分析法」)、医薬品化学(「C-4 薬学の中の医薬品化学」)、生薬学・天然物化学(「C-5 薬学の中の生薬学・天然物化学」)、生理学・解剖学及び免疫学(「C-7 人体の構造と機能及びその調節」)の理解が深化します。こうして、後継的に、また発展的に学ぶ、薬学のオリジナリティーでもある薬剤学・薬物動態学(「D 医療薬学」)、衛生薬学(「E 衛生薬学」)、薬理学及び感染症学、感染症治療学を含む病態治療学(「D 医療薬学」)の科学的な根幹が形成されます。
D:医療薬学
薬学教育モデル・コア・カリキュラムにおける「A 薬剤師として求められる基本的な資質・能力」を生涯にわたって醸成するために、「B 社会と薬学」で学ぶ薬剤師の責務を常に念頭に置き、「C 基礎薬学」で学んだ医薬品の構造と性質、生体の機能と恒常性などの学修成果を、「E 衛生薬学」の疾病予防、公衆衛生、及び「F 臨床薬学」における個々の患者への責任ある薬物治療の実践に結びつけることを目的とした大項目です。 「F 臨床薬学」では、薬物治療を個別最適化するために、患者ごとに異なる状況へ十分に配慮した上で薬物治療を選択、実施、評価する必要があります。そのため、本大項目は責任ある薬物治療を実践するための基本となる疾患の病態生理と薬物の作用のメカニズムを関連付けた系統的な理解、ガイドラインによる標準化された治療方針、根拠に基づく医療を提供するために、医薬品情報をもとに薬物の有効性・安全性の適切な評価、薬物動態の理論を理解した上で、適切な用法・用量・剤形の選択と処方箋調剤の基本を一般論として修得し、「F 臨床薬学」で患者個々の薬物療法を実践するために使える学力を身に付けます。 また、「E 衛生薬学」で求められる薬剤師のもう一つの重要な使命である地域における予防、衛生を実施する際の基本となる事項を学修します。
E:衛生薬学
薬学教育プログラムにおける「B 社会と薬学」、「C 基礎薬学」、「D 医療薬学」の学修をもとに、科学的根拠と最新の解析技術に基づいて、社会・集団における環境要因によって起こる疾病の予防や健康被害の防止、感染症の予防・まん延防止、健康の維持・増進に必要な栄養・食品衛生、人の健康に影響を与える化学物質の適正な管理と使用、環境保全等について学修します。本大項目の学修は、「F 臨床薬学」における薬物治療、医療安全等の学修につながり、さらに、「E 衛生薬学」の学修を通じ、国民の健康な生活の確保、健全な社会の維持・発展に貢献するために、レギュラトリーサイエンスの視点で人の健康に係る公衆衛生、食品衛生、環境衛生上の課題を発見し、その解決に取り組む能力を身に付けます。
F:臨床薬学
「C 基礎薬学」で学ぶ化学物質や生体の基礎知識を基に、「D 医療薬学」で学ぶ疾患や医薬品の知識を総合的に活用して、適切な薬物治療の計画を立案し、患者・生活者中心の視点から個別最適な薬物治療を提供します。「B 社会と薬学」で学ぶ法令や規範、倫理等を遵守し、患者、生活者の立場を尊重したコミュニケーションにより、多職種との連携を円滑に行い、質の高い薬学的管理によるファーマシューティカルケアを実践します。また、「B 社会と薬学」で学ぶ健康管理や「E 衛生薬学」で学ぶ公衆衛生、感染制御、環境保全等の知識を、医療現場や地域で活用して、医療、保健、介護、福祉の向上に貢献する能力を身に付けます。
G:薬学研究
大項目B?Fにおいて学んだ知識や技能を活用して、自らが探究すべき薬学的な課題を発見し、課題に係る情報の収集と解析・評価に基づいて研究課題の設定と研究計画の立案を行います。研究計画に沿って、主体的に研究を行い、その結果についての学術的な解析と考察により結論を導きます。こういった科学的な探究を通して、薬学や医療の発展に貢献する研究に必要な課題発見能力・問題解決能力を身に付け、また研究において求められる基本的な姿勢を理解し、自らの研究を科学的、倫理的、人道的に遂行する資質を涵養します。